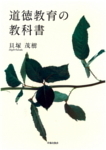
貝塚茂樹 著
「神社新報」 2009年6月15日
高橋陽一 (武蔵野美術大学教授)
「道徳教育」を学ぶコンパクトな入門書
本書は大学における教員養成のための教科書として、全三部十四講で構成されてゐる。第一部では明治の修身科から現在に至るまでの道徳教育の歴史が語られ、第二部では昨年告示された新しい学習指導要領に依拠した学校での道徳教育の実践が解説され、第三部では個性や知育、愛国心などのテーマが論じられる。
大学での道徳教育の講義は、担当者の専門分野に傾きがちであるが、本書は歴史と実践と課題にわたり、バランスをとる工夫がなされてゐる。また教育史家としての見識からさまざまな議論が紹介され、概説書とはいへ、著者が専門とする戦後道徳教育史は新しい知見が得られる貴重な内容となってゐる。
ただ戦前の記述には粗さもある。二段落の教育勅語の原文を三段落に分けて改行した資料を掲げて、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」で始まる部分を「私は、私達の祖先が」とする「口語訳文」を紹介してゐる。原典を任意に改行したり、君臣の秩序を意識して書かれた文章を「私」や「私達」と意訳するのは如何かと思はれる。巻末には資料として加工してゐない原文が掲載してあるが、戦後風に意訳するのではなく、歴史的な文意の説明が望まれる。
公立学校での「宗教的情操」をめぐって平行線の議論をするよりも、地域や家庭で、自在で多様な宗教教育をおこなふことが実質的な道徳教育の発展へと繋がる。そのためにも、学校教育をめぐる歴史やその困難さを考へることは、有意義であらう。いくつか批判を記したが、本書はコンパクトな入門書ながらしっかりした内容を持つ書籍であり、道徳教育に関心のある方々にお勧めしたい一冊である。

