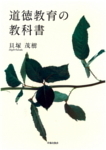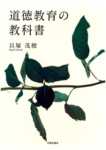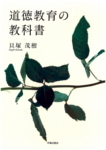山田 明 著
日本教育学会 『教育学研究』 第76巻第2号(2009年6月)
飯田浩之 (筑波大学)
「サービス・ラーニング」が国内で知られるようになったのは最近である。まして実践となると数えるほどである。タイトルに冠した書籍もほとんど刊行されていない。サービス・ラーニングは国内では新しい取り組みである。しかるに米国ではかなり以前から教育界に導入されてきた。1990年代には「コミュニティ・サービス法」などを背景に行政支援が行われ、急速に普及した。著者は、米国で普及してきたサービス・ラーニングの効果に期待を寄せ、日本の高校への導入・普及を目指している。本書において著者はその可能性を検討し、導入・普及の見通しをつけようとしている。著者が言わんとするところは明快である。日本への導入は制度的に可能であり効果も認められる。但し、普及のためには実施をサポートするシステムが不可欠である。
本書の特徴は、著者のサービス・ラーニングに期するところの大きさとその内実にある。まずはそれに耳を傾けるとしよう。
著者によれば「サービス・ラーニング」とは、「地域社会のニーズに基づき、学校の教科カリキュラム(教科学習)に関連したサービス活動を通じて社会貢献することで学びの深化を図る学習形態であり、事前準備・活動・振り返り・祝福の経過を踏んだ計画的・組織的・継続的な教育方法である。」
では何故、サービス・ラーニングなのか。第1章において著者は、行政機関が行った調査の結果のもとに、日本の高校が不登校、いじめ、高校中途退学、学力低下など様々な問題を抱えていることを指摘する。そしてこれらの問題の背景には、生徒の自尊感情の低さがあると指摘する。自尊感情は主体的な社会参加のなかで培われる。サービス・ラーニングは、主体的な社会参加の資質及び能力の涵養につながる教育方法である。それを日本の高校に導入・普及したならば、生徒の自尊感情は向上する。以て、高校が抱える問題が解決に向かって動き出す。著者のサービス・ラーニングに期するところの一つは、この点にある。
著者がサービス・ラーニングの導入・普及を主張するいま一つの理由は、高校教育改革の方策としての意義にある。この点を著者は、米国におけるサービス・ラーニングの理念と実践から引き出している。すなわち第2章では米国のサービス・ラーニングの理論とそれに期待される教育・学習効果が紹介されている。また、1960年以降の米国の教育改革においてサービス・ラーニングが果たしてきた役割が明らかにされている。そこで強調されているのは、サービス・ラーニングが規律の涵養と学力の向上をともに実現できる教育方法としていちづけられてきたことである。さらに、その効果が実証されているという事実である。翻って日本の高校教育改革の動きをみると「ゆとり」と「学力向上」の狭間で揺れている。「ゆとり」か「学力向上」かの二者択一を迫るような状況にある。この点、サービス・ラーニングは生徒のサービス活動と教科の学習を結ぶ教育方法であり、「ゆとり」と「学力向上」を共に実現できる方法である。かくしてサービス・ラーニングは高校教育改革の切り札として期待できる、というのが著者の主張である。
では、このようなサービス・ラーニングを日本の高校へ導入し普及させることは可能なのか。本書の特徴の二つ目は、制度と効果の両面からこの点についての検討が行われている点にある。制度的な枠組みが用意されていなければサービス・ラーニングを学校教育現場に導入することは難しい。実際に教育・学習効果がなければ導入・普及に意味がない。著者は第3章において、この点についての検討を執拗なほどに進めている。
まず、前者について「学習指導要領」が取り上げられる。高校にサービス・ラーニングを導入するためにはそれを「学習指導要領」のなかに位置づけることが必要である。「教育学習」においてはどうか。「普通教育及び専門教育に関する各教科・科目」「学校設定科目・教科」「課題研究」のなかで展開可能。むしろその教育効果を高めるものとしても位置づけられる。「特別活動」「総合的な学習の時間」の枠においてはどうか。「学習指導要領」を超えた導入の仕方もあり得るのでは……。実際、著者自身が関わっている「サービス・ラーニング・フォーラム宗像」の例もある。著者は、このようにしてサービス・ラーニングが制度的に日本の高校に導入し得るものであることを説いていく。
後者においては、著者が大学や高校、主宰するNPOで取り組んだ実践プログラムについて効果の実証が試みられている。使われているデータは、取り組みのなかで実施した質問紙調査の結果や振り返り日誌、参加者へのインタビュー資料などである。種々の結果が示されるなかで、サービス・ラーニングが学生・生徒の自尊感情の向上、学習意欲の高揚、主体的な社会参加の資質及び能力の獲得につながったことが示されている。
かくして日本の高校にサービス・ラーニング導入・普及の道が開かれると著者は言う。ただ、著者はその導入・普及には克服すべき課題が存在することも忘れていない。この課題の指摘に本書の第三の特徴がある。本書の第4章では、サービス・ラーニングを日本に導入する場合を視野に、米国の状況を踏まえて、その課題の検討がなされている。
ここで特に著者が力説するのは、学社連携の観点からの課題である。米国の実践は地域教育とそれを支える地域教育組織の充実によって支えられている。このことを踏まえた場合、日本においてサービス・ラーニングを導入・普及させるためには、それを支えるサポート・システムを構築することが課題となる。著者は、自身が関わっているNPOや市民フォーラムを例にNPOのような中間組織がコーディネーターとなるサポート・システム、行政と市民が協働するサポート・システムの構築を提案する。
以上、本書の特徴を述べてきた。先述のように本書の主旨は明快である。米国の実践に学び、サービス・ラーニングを日本の高校に導入・普及することで生徒の主体的な社会参加の資質・能力を培いたい。以て、彼ら・彼女らの自尊感情を高め、今日の教育問題の解決に寄与したい。それは教育方法の次元における高校教育改革に他ならない。実際、制度的な基盤も存在し、教育・学習効果も認められる。必要なのは、実践を支える地域のサポート・システムである。
著者は、米国に範をとりながら自らもそれを実践するなかでサービス・ラーニングのプログラム化を目指している。本書の主旨の明快さは、自身の実践経験に裏付けられている。その点で本書は米国のサービス・ラーニングの単なる紹介を超えている。日本における導入・普及の布石として意味をもっている。ただ、主旨の明快さは細部に拘って読んだ際に幾つかの疑問を生じさせる。触れられていないところがあるように思えてくる。
一つは、効果の実証性である。著者は、アメリカの研究を引用しつつサービス・ラーニングの効果を主張する。同時に、自身の実践で質問紙調査等を実施し、効果の検証を試みる。しかし、その検証は必ずしも妥当性・信頼性の高いものではない。使われているデータが高校ではなく大学での実践から得たものであったり、質問が米国で行われた調査の直訳であったりしている。分析においては不自然な比較がなされていたり、効果が表れていない結果について無理に解釈を行っていたりするところも見て取れる。調査対象者が実践に参加した学生・生徒であるところから、その数も限られている。確かに導入にあたっては、効果を確と示す必要があろう。しかし、果たして現時点でそれを急いで行うことが得策であるかどうか。牽強付会になりかねない効果の検証はかえって疑念を抱かせるものとなりはしまいか。著者の主旨に賛意を抱くだけに、その点が懸念される。
第二に、日本における導入・普及において地域のサポート・システムが重要であることは評者も強く感じるところである。しかし、同時に課題は学校サイドにもあると思われる。サービス・ラーニングは「計画的・組織的・継続的な教育方法」である必要がある。それを担保するものは、まずもって「学校」ではあるまいか。サービス・ラーニングの導入・普及に必要なのは、学校サイドの体制づくりである。著者は、主宰するNPOを中心にサービス・ラーニングの実践にあたっており、その立場からサービス・ラーニングの導入・普及を論じている。それはそれで立場が明確であり、本書の主旨に明快さを与えている。しかし、立場が明確であることによって視野から除外されるところも生じてくる。それが学校サイドの課題である。むろん、著者自身、この点は十分に意識していることと思われる。今後の検討に期待したいところである。
第三に、サービス・ラーニングと教科学習との関連についてである。サービス・ラーニングで重要なのは、実施されるサービス活動が学校の教科カリキュラムに関連していることである。著者がイギリスのシチズンシップ教育ではなく米国のサービス・ラーニングに範を取ろうとするのも、後者が教科学習に関連し、学力の向上に寄与し得ると見るからである。だが、その「関連」については、サービス・ラーニングが生徒の自尊感情を向上させ、それが彼らの学習意欲の向上に結びつき、結果として生徒の学力を向上させるとするに止まっている。それはそれで明確な視点ではある。しかし、それだけでよいであろうか。
一般に「サービス・ラーニングと教科学習との関連」については、「事前準備や振り返りが必要」とされるだけである。指導者の構えに帰せられて終わる傾向にある。だが、「関連」の本質に迫ろうとするならば、教科学習の拠って立つ「知」とサービス活動に内属する「知」との関連を問わざるを得ないのではあるまいか。評者の見るところ、この「関連」の問題は、「知の在り方」の問題に帰着する。この点について著者は両者の関連を、「自尊感情」「学習意欲」といった「個人の心理」で結びつけている。それはそれとして著者独自の視点であり、異論があるわけではない。しかし、この「関連」は「個人の心理」を超えて議論されるべきではあるまいか。本書の課題というよりサービス・ラーニングそのものの課題であるのかもしれないが、この点が疑問として残される。
冒頭でも述べたように日本でサービス・ラーニングについて書かれた書籍は数少ない。実践も未だ始まったばかりである。本書を通じて強く感じ取れるのは、著者の「サービス・ラーニング」への期待の大きさと、その導入・普及に向けた意気込みの強さである。本書が日本の高校におけるサービス・ラーニング導入・普及の糸口となることは間違いない。サービス・ラーニングに関心をもつ一人として、本書を糸口に日本にこの教育方法が広がり、更なる研究が行われることを期待したい。